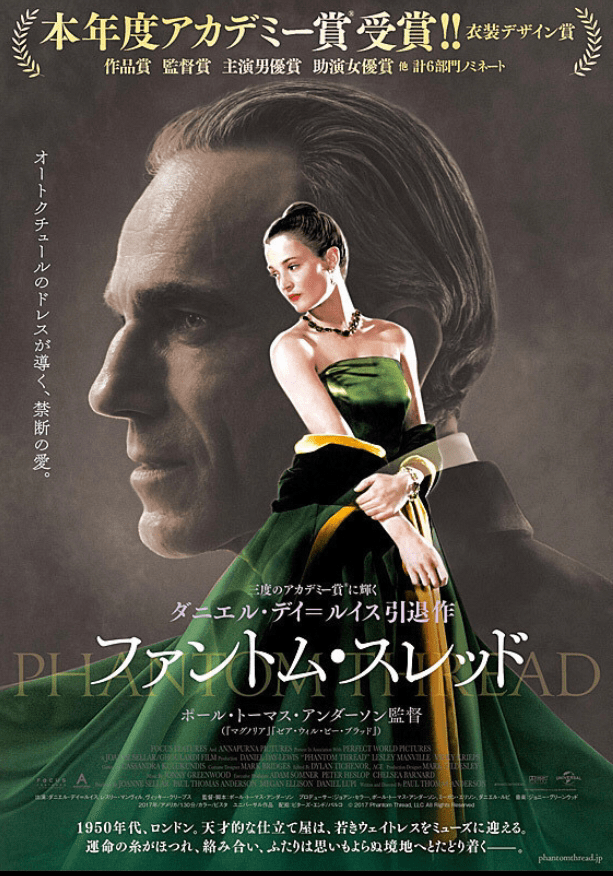・
・
「すごいものを観た」という感覚が鑑賞直後からずっと心に残っている。
映画を観た、というには映画らしくなかった。
もちろん文法的にはちゃんとした映画なのだけど、映画の[ジャンル分け]とか[登場人物のステロタイプ化]とかの、映画を分かり易くする[紋切り]が廃されていて、映画を観たというよりは【ひとが生きる】【ひとと生きる】ことの不条理さと尊さを感じ続けた2時間だった。
印象に強く残るシーンはいくつもある。
・
・
[F.マクドーマンドとW.ハレルソンとの関係描写]
最初に描かれる、マクドーマンドの自宅のブランコに座ってのやりとり。
二人の表情や空気から感じ取れるのは、“ベテラン先生と生意気な生徒”、あるいは互いを“同志”として認めているような雰囲気は恐らく、マクドーマンドの娘が殺害され、捜査の上でふたりがやりとりする中で培われたものだ。
続いて警察所内での尋問シーン。
自分を脅迫した歯医者をゴアなやり口で返り討ちにしたマクドーマンドも、ハレルソンの吐血には動揺している。
そしてハレルソンの自死後、彼が生前にマクドーマンドに宛てた手紙において明かされる、彼女へのメッセージ。
これらのシーンはいずれも、二人が対立する間柄ではなく信頼関係で結ばれていたことを感じさせる。
マクドーマンドが広告を出した理由は、ハレルソンの中で燻ったままの炎を彼の生きている間に完全燃焼させるためでもあったはず。
しかし二人のそんな信頼関係を、町の人間もハレルソンの妻も知ることはない。
・
・
[マクドーマンドとその家族の会合]
マクドーマンドが出した看板の存在を知り、別れた夫(J.ホークス)が自宅に訪れ、息子(L.ヘッジズ)とともに、期せずに家族の再会となる。
夫婦が離婚した原因には彼のDVもあり、互いの言動に一触即発となる状態となるが、ひっくり返ったテーブルを親子がいっしょに片づける。
また、元夫婦のふたりは娘を失った哀しみでは手を取り合いつつも、その次の瞬間には互いを非難する言葉を浴びせる。
“憎しみ”と“共感”が同時に存在する、家族/夫婦という関係性のやっかいさの描写がとてもリアルだった。
・
・
[病室でのS.ロックウェル]
マクドーマンドによる警察署への放火に巻き込まれた重傷のロックウェルが入院した相部屋には、自分が腹いせにボコボコにしたC.L.ジョーンズがいた。
火事の直前に読んだハレルソンからの手紙により改心したロックウェルは「すまなかった」と涙を流す。
憤りが消えないジョーンズは怒りに震えながらもオレンジジュースを差し出す。
文字通り“火”に焼かれることで罪を償い、涙とオレンジジュースという“水”により清められ生まれ変わったロックウェルがその後にとった行動の価値については言うまでもない。
・
・
[マクドーマンドとロックウェルの車中シーン]
一連の出来事に決着をつけるためにアイダホに向かうことにする二人。
それぞれの家族に別れを告げ、銃を手に車を走らせる。
車内での静かな二人の会話が示す、それぞれの気持ちの変化を描写した直後に、画面は暗転しエンドロールとなり、その場面がラストシーンであったことを告げられる。
“え、ここで終わり?”という驚きとともに涙が溢れた。
このシーンで泣いた、というよりも、このシーンをラストシーンとした監督のやさしさに泣いた。
このあとの二人はどうなるのだろう。
アイダホに向かうにしても引き返したにしても、それぞれが背負った苦しみは無くなることはないだろう。
しかし苦しみと生きていく中でも、希望を抱いたり憎しみが和らぐ瞬間はきっとある。
その瞬間を忘れずに抱き続けることでひとは生きていける。
ハレルソンが生前に妻に宛てた手紙にあった「苦しみが思い出になるよりも、美しい思い出を最後に残したい」という言葉のように。
(2018.02)